副業の労働時間はどう管理すべき?厚労省ガイドラインに基づく実践マニュアル
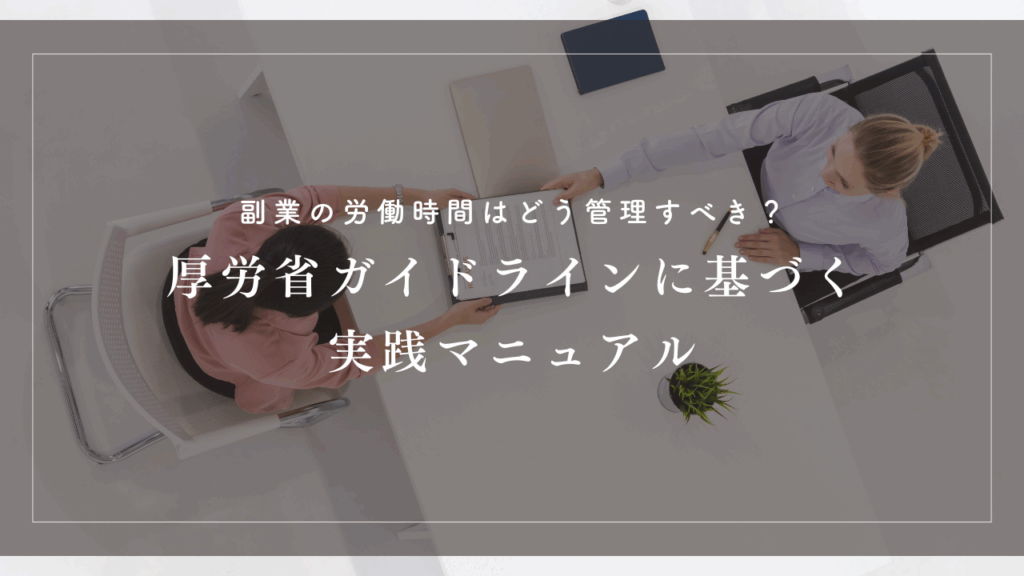
近年、働き方改革の推進により副業兼業の促進に関するガイドラインが注目される中、副業を認める企業が急増しています。しかし、「副業を解禁すれば従業員のモチベーションが上がる」と考える一方で、労働時間の管理や法的リスクに頭を悩ませている担当者も多いのではないでしょうか。
私自身、フリーランスライターとして本業を持ちながら、副業でモデル活動を行っている経験から、副業者の立場では「本業に迷惑をかけずに副業をしたい」「でも労働時間の管理はよくわからない」という不安を常に感じています。企業側としては、こうした労働者の気持ちを理解しつつ、社員の副業を適切に管理することが求められています。
実は、副業における労働時間の通算管理は、労働基準法上の義務であり、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」でも明確に示されています。
本記事では、副業・兼業を認める企業が知っておくべき労働時間管理の実務ポイントをガイドラインに基づいて詳しく解説していきます。
「副業を認めたいけれど、どのように管理すれば良いかわからない」「労働基準法違反のリスクを避けたい」とお考えの人事・労務担当者の方に、実践的な管理モデルとは何か、そして現場で使える具体的な対応策をお伝えします。
厚生労働省ガイドラインの概要
副業・兼業の労働時間管理については、労働基準法第32条(法定労働時間)および第38条第1項(事業場を異にする場合の通算)の規定に基づき、複数の事業場で働く労働者の労働時間は合算して管理することが義務付けられています。
厚生労働省が策定した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(2022年7月改定)でも、この点について次のように明記されています。
副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者は、労働時間を通算して管理する必要がある。
(出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」)
さらにガイドラインでは、労働時間把握の方法として自己申告制を活用することや、健康確保措置、情報漏えい防止などの観点からの管理体制整備が推奨されています。
参考リンク:
厚生労働省|副業・兼業の促進に関するガイドライン
副業解禁の時代、企業に求められる「副業管理」とは?

副業を許可する企業が増えている背景
働き方改革関連法の施行以降、副業・兼業の解禁は多くの企業にとって避けて通れない課題となりました。
副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされており、裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが適当であるといえます。
厚生労働省が発表したデータによると、副業を認める企業は年々増加傾向にあり、特にIT企業や新興企業を中心に、人材確保と従業員の成長促進の観点から副業を積極的に推進する動きが見られます。
労働者側の副業志向も高まっており、「スキルアップのため」「収入増のため」「将来への備えのため」といった多様な理由で副業を希望する社員の数は増加しています。私が副業でモデル活動を始めたのも、本業のライティングとは異なる仕事で収入を得られるようにし、将来的なキャリアの幅を広げたいという思いからでした。
このような労働者のニーズに応えるため、企業は副業を「禁止」から「管理」へとスタンスを変える必要があります。
ただし、副業を認めることは単に就業規則を変更すれば良いというものではなく、適切な労務管理体制の構築が不可欠です。
副業を管理するために企業が行うべきこと
副業を認めるにあたって、企業がまず着手すべきは 「就業規則の整備」と「管理体制の構築」 です。
これらを曖昧にしたまま副業を許可してしまうと、労働時間の通算管理不足や情報漏えい、健康被害など、法的リスクや企業秩序の乱れにつながる恐れがあります。
1. 就業規則の整備
厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、副業を認める場合でも、許可条件や制限事項を就業規則に明記することが推奨されています。
副業の定義や対象範囲、申請方法や審査基準などを明文化することで、労働者が安心して副業を申請でき、企業側もトラブル発生時に明確な基準をもとに対応できます。
2. 管理体制の構築
就業規則の改定だけでは、副業管理は機能しません。運用面での体制整備が不可欠です。
労働時間の通算管理や健康管理、情報管理とコンプライアンス、相談・申告窓口の設置などを行うことが求められます。
適切な就業規則と管理体制は、企業と労働者双方の安全を守る「土台」です。
これらを整備することで、副業は単なる「収入のための手段」ではなく、労働者のキャリア形成や企業の競争力向上につながる仕組みとして機能します。
「副業管理」とは何を指すのか
副業管理とは、労働者が本業と副業を両立する際に生じる様々なリスクを、企業が適切にコントロールすることを指します。具体的には以下の要素が含まれます。
労働時間の管理:法定労働時間や時間労働の上限規制への対応、労働時間通算の実施
健康管理:過重労働による健康リスクの防止、安全配慮義務の履行
情報管理:機密情報の漏洩防止、競業避止義務の徹底
労務管理:副業許可の条件設定、届出制度の運用
厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」において、副業は労働者の主体的なキャリア形成や企業の優秀な人材確保につながる一方で、適切な管理なくしては労働基準法違反や健康被害のリスクがあると明示しています。
私自身の経験でも、副業のモデル撮影が本業のライティング業務の繁忙期と重なった際に、少しだけ無理をしてしまい、体調を崩しかけたことがありました。勤務先への事前相談と調整により大事には至らなかったものの、私に万が一のことがあればクライアントに迷惑をかけてしまっていた可能性があると気づかされ、深く反省しました。
また、その際に勤務先から「自社以外での労働時間が把握できず、体調管理が心配だ」という指摘も受け、副業が本業に影響を及ぼすリスクについて、あらためて自覚するきっかけにもなりました。
後になって知ったのですが、万一の事態が起きれば企業側にも安全配慮義務の観点から責任が生じる可能性があるとのことで、私の行動が結果的に会社に負担をかけかねなかったことを、心から申し訳なく思いました。
同時に、私の体調や働き方を真剣に心配し、言葉にしてくれた勤務先の姿勢には大きな信頼と感謝を感じました。労働者のキャリアや想いに寄り添いながら、リスクに備えてくれる企業があることは、とてもありがたいことだと実感しています。
このような場面で、企業側に明確な副業管理制度があることで、労働者も安心して副業に取り組むことができると感じています。
副業を許可する際の就業規則・労務管理の整備ポイント
就業規則で明記すべき内容
副業を認める際は、就業規則の改定が必須となります。明記すべき主な内容は以下の通りです。
副業許可の条件
本業への支障がないこと
競業避止義務への抵触がないこと
会社の信用を損なわないこと
健康保持義務を果たすこと
届出制・審査制のフロー
事前申請の義務化
審査基準の明確化
承認・不承認の判断プロセス
変更・終了時の報告義務
私自身、本業の勤務先からは「競合他社での活動は控えること」「健康管理に十分注意すること」といった条件が提示されています。これらの条件は、労働者の立場からも納得しやすく、むしろ安心して副業に取り組める環境を作ってくれています。
健康管理と安全配慮
副業による過重労働は、企業にとって安全配慮義務違反のリスクとなります。特に注意すべき点は以下の通りです。
ストレスチェック義務の拡大適用
本業と副業を合わせた総労働時間が長時間に及ぶ場合、通常以上に健康リスクが高まります。年1回のストレスチェック実施時には、副業の有無や労働時間も考慮した健康状態の把握が重要です。
過労死ライン(月80時間)の考慮
厚生労働省が示す過労死認定基準では、月80時間を超える時間外労働が健康障害発症の重要な要因とされています。副業を含めた総労働時間がこの基準を超えないよう、継続的なモニタリングが必要です。
私が副業でモデル活動をする際も、特に撮影が深夜に及ぶ場合は本業への影響を慎重に考慮し、必要に応じて案件を調整しています。企業側からこのような健康配慮の姿勢を示してもらえることで、労働者も責任を持って副業に取り組めます。
懲戒事由になる副業ケース
副業が懲戒処分の対象となるケースも明確にしておく必要があります。
業務怠慢・本業への支障:副業の疲労により本業でのパフォーマンスが著しく低下した場合
機密漏洩・競業避止義務違反:本業で得た情報を副業で利用した場合、競合他社で活動した場合
無断副業・虚偽申告:許可を得ずに副業を行った場合、労働時間を過少申告した場合
これらの基準を事前に明示することで、労働者にとっても予見可能性が高まり、適切な副業活動が促進されます。
副業の労働時間は通算管理が必要?ガイドラインのポイント
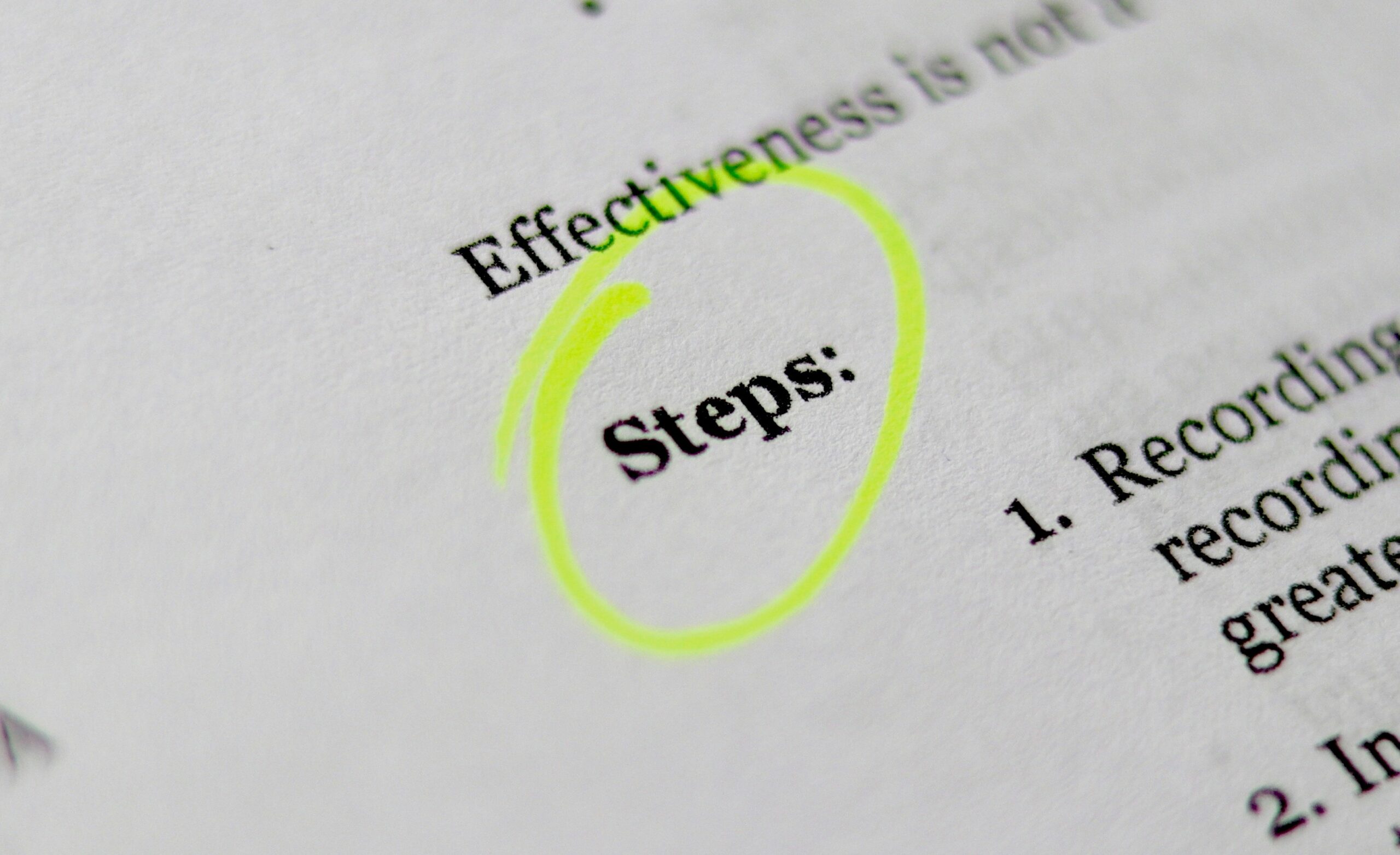
労働時間通算の基本ルール
労働基準法第32条および第38条第1項では、労働者が複数の事業場で労働契約を締結した場合、それぞれの労働時間を通算して、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えないように管理することが義務付けられています。
さらに厚生労働省のガイドラインでも、「副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者は、労働時間を通算して管理する必要がある」と明記されています。
つまり、企業は事業場を異にする場合であっても、ふたつ以上の事業所での労働時間の通算が必要で、それらを合算して管理しなければならないということです。
ここで重要なのは、「使用者B」(後から労働契約を締結した事業者)が通算管理の責任を負うという点です。例えば、労働者がA社で1日6時間勤務し、その後B社で4時間勤務する場合、B社は合計10時間のうち法定労働時間を超える2時間分について、割増賃金の支払い義務を負います。
この仕組みは、「本業と副業のどちらが責任を負うのか」という現場でよくある疑問に対する明確な答えでもあります。先に契約を締結した事業者(使用者A)の所定労働時間が既に確定している以上、後から契約する事業者(使用者B)が労働時間の上限管理を行うのが合理的とされています。
厚労省ガイドラインの注目ポイント
厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、労働時間通算における実務上の取扱いについて詳しく解説されています。特に注目すべきは、自己申告制の原則です。
ガイドラインによると、「使用者は、労働者からの自己申告により、副業・兼業先での労働時間を把握することが考えられる」(厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」)と明記されています。
そのうえで、「その労働時間を通算して管理する必要がある」ことも合わせて示されており、企業には労働者の申告を前提とした合理的な時間管理の体制が求められています。
私が副業でモデル活動を行う際も、撮影時間の管理は自分自身で行っており、本業の勤務先に月次で報告しています。この経験から感じるのは、労働者側にも正確な時間管理の意識と責任が求められているということです。
よくある誤解とリスク
副業の労働時間管理において、企業が陥りやすい誤解がいくつかあります。
誤解①「副業は労働時間に含まれない」
→実際は、雇用関係がある副業は労働時間として通算対象になります。
誤解②「36協定は本業のみで十分」
→労働時間を通算した結果、時間外労働の上限を超える場合は36協定違反となります。
誤解③「副業先の労働時間は把握不要」
→使用者Bとしての立場では、労働時間の把握と割増賃金の支払いが必要です。
これらの誤解により、労働基準法違反や未払い賃金の問題が発生するリスクがあります。実際に、労働基準監督署による指導事例も増加傾向にあり、適切な対応が急務となっています。
実務で使える副業の労働時間管理モデル

厚労省が示す「管理モデル」とは
厚生労働省が示す管理モデルの基本的な考え方は、「先契約企業の所定労働時間を前提とし、後契約企業が超過分の責任を負う」というものです。
具体的には以下のような流れになります:
使用者 A(先契約企業):所定労働時間が1日7時間、週35時間
使用者 B(後契約企業):労働者の副業受け入れ時に、A社での労働時間を確認
通算管理:A社7時間+B社3時間=1日10時間となる場合、B社が2時間分の割増賃金を支払い
この管理モデルとは、複雑に見えますが実際の運用では比較的シンプルです。
労働時間把握の実務例
実際の労働時間把握では、以下のような自己申告用のテンプレートが有効です。
副業労働時間申告書(例)
申告対象月:○年○月
本業での月間労働時間:○○時間
副業での予定労働時間:○○時間
1日の最大労働時間:○○時間
週の最大労働時間:○○時間
社内届出制度としては、副業開始前の事前申請と、月次での実績報告を組み合わせる方法が一般的です。事前申請では副業内容と予想される労働時間を把握し、月次報告で実際の時間外労働発生状況を確認します。
現場でよくある工夫と対応策
実際の運用では、多くの企業が独自の工夫を凝らしています。よくある対応策をご紹介します。
「副業は週○時間まで」の社内規定
法定労働時間の範囲内で、副業の上限時間を設定する方法です。例えば「副業は週10時間以内」「1日の合計労働時間は10時間以内」といった規定を設けることで、労働 時間 の 上限管理を簡素化できます。
私が本業で相談を受けた企業では、「本業40時間+副業8時間=週48時間」を上限とし、この範囲であれば時間外労働の割増賃金も予測しやすくなったという事例がありました。
副業を業務委託・請負契約にする運用ケース
労働時間通算を避ける方法として、副業を雇用関係ではなく業務委託や請負契約で行うケースも増えています。この場合、労働者性がないため労働基準法の適用外となり、労働時間の通算義務は発生しません。
ただし、実質的に指揮命令関係がある場合は労働者性が認められる可能性があり、慎重な判断が必要です。
実は、副業としてモデルのお仕事を続けていくとこの問題に直面することは多々あります。その点については別の記事でまとめる予定です。
労働時間の管理ツールとシステム導入のポイント
副業解禁の流れを受けて、労働時間の管理を効率化し、法令遵守を徹底するためには、労働時間管理ツールやシステムの導入が不可欠です。厚生労働省のガイドラインや労働基準法の規定に沿った運用を実現するため、導入時に押さえておきたいポイントを解説します。
1. 労働時間の通算管理の徹底
本業と副業の労働時間を通算して管理することは、労働基準法第38条第1項で明確に定められています。たとえ事業場を異にしても、労働者の労働時間は合算して把握しなければなりません。管理ツールやシステムには、複数の勤務先での労働時間を一元的に記録・集計できる機能が求められます。自己申告制を補完する形で、労働者が本業と副業の労働時間を簡単に入力・報告できる仕組みを整えましょう。
2. 時間外労働の上限設定とアラート機能
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働の上限が厳格に定められています。管理システムには、時間外労働の上限を自動で判定し、上限を超えそうな場合にアラートを出す機能があると安心です。これにより、労働時間が法定を超えた場合のリスクを未然に防ぐことができます。
3. 割増賃金の自動計算・支払い機能
労働時間が法定労働時間を超えた場合、割増賃金の支払いが必要です。管理ツールには、労働時間の通算結果に基づき、割増賃金の自動計算や支払い処理まで一括で行える機能があると、担当者の負担を大幅に軽減できます。特に副業を認める企業では、割増賃金の支払い漏れがないよう、システム化が重要です。
4. 厚生労働省推奨の「管理モデル」への対応
厚生労働省が推奨する管理モデルでは、副業開始前に労働者と先契約企業の所定労働時間、後契約企業の労働時間を合算し、単月100時間未満・複数月平均80時間以内で管理することが求められます。システム導入時には、この管理モデルに沿った労働時間の集計・上限設定ができるかを必ず確認しましょう。
5. データ分析による労働時間の最適化
労働時間管理ツールには、蓄積したデータをもとに労働時間の傾向や時間外労働の発生状況を分析できる機能があると便利です。これにより、労働者ごとの働き方や副業の影響を可視化し、労働時間の最適化や健康リスクの早期発見につなげることができます。
6. 社会保険との連携
労働時間の管理は、社会保険の適用判定とも密接に関係しています。特に副業を複数掛け持ちする場合、各勤務先での労働時間を正確に把握し、社会保険の加入要件を満たしているかどうかを判断する必要があります。管理システムには、社会保険の適用判定をサポートする機能があると、より安心です。
7. セキュリティ対策の徹底
労働時間のデータは、個人情報や企業の機密情報を含むため、セキュリティ対策も欠かせません。システム導入時には、アクセス権限の設定やデータの暗号化、バックアップ体制など、情報漏洩リスクを最小限に抑える仕組みを必ず確認しましょう。
これらのポイントを押さえて労働時間管理ツールやシステムを導入することで、労働基準法の遵守はもちろん、労働者の健康管理や割増賃金の適正な支払い、社会保険の適用判断まで、幅広い労務管理業務を効率化できます。副業時代の新しい働き方に対応するためにも、最新の管理ツールの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
【チェックリスト】副業制度設計に必要な対応まとめ
副業制度を導入する際の必須対応事項をチェックリスト形式でまとめました。
✅ 労働時間通算の対応は明確か
労働時間の把握方法は確立されているか
自己申告制の運用ルールは整備されているか
割増賃金の支払い体制は構築されているか
✅ 使用者Bの責任理解はあるか
後契約企業としての義務を理解しているか
時間外労働の上限規制への対応は万全か
36協定の見直しは完了しているか
✅ 健康リスク対策の導入済みか
過重労働防止策は講じられているか
ストレスチェックの拡大適用は検討済みか
安全配慮義務の履行体制は整っているか
✅ 規定・申告制度の運用体制はあるか
就業規則の改定は完了しているか
副業許可の審査体制は構築されているか
継続的な運用・見直しの仕組みはあるか
これらの項目すべてにチェックが入って初めて、適切な副業制度の運用が可能になります。一つでも欠けている項目があれば、法的リスクや労務管理上の問題が発生する可能性が高まります。
副業は「自由」ではなく「制度設計」で活かす時代へ

副業解禁の流れが加速する中で、「副業を許可する=従業員の自由に任せる」という発想では、企業・労働者双方にとってリスクが生じます。適切な制度設計と継続的な労務管理こそが、副業を企業の競争力向上につなげる鍵となります。
私自身の副業経験からも、明確なルールと適切なサポート体制がある企業ほど、労働者の信頼と生産性が向上することを実感しています。副業による新たなスキル習得や人脈形成は、最終的に本業にも良い影響をもたらします。
副業管理は単なるリスク対策ではなく、中長期的な人材活用戦略として捉えることで、企業の持続的成長と従業員のキャリア発展の両立が実現できるのです。労働時間管理の適切な運用から始めて、段階的に制度を成熟させていくことが、副業時代における企業経営の成功要因となるでしょう。