副業禁止は違法?就業規則と会社員が知るべきリスクと対策
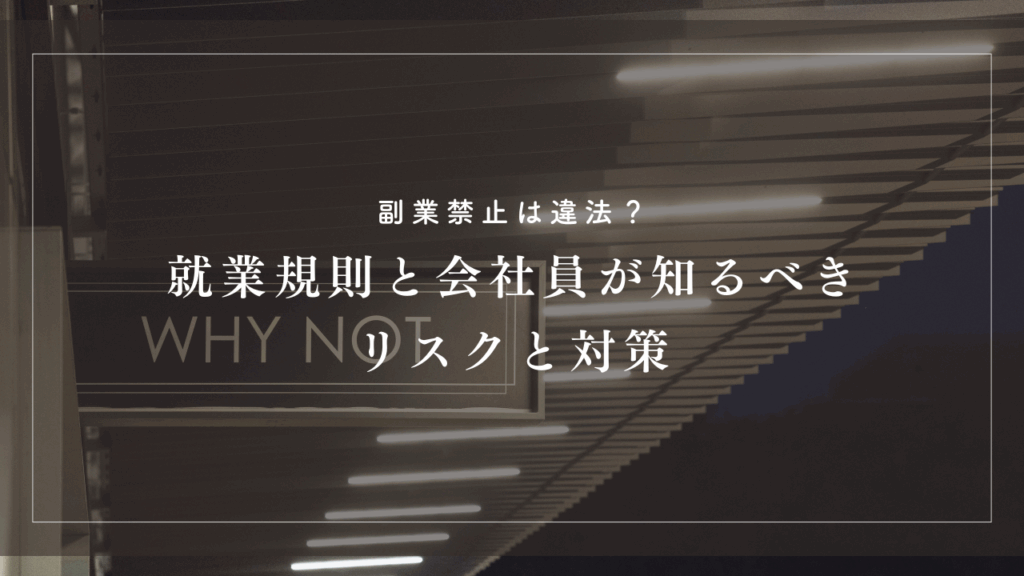
政府が副業を推進する現代でも、多くの企業が従業員の副業を禁止しているのが現実です。「副業解禁の時代なのに、うちの会社は副業禁止のまま…これって違法じゃないの?」そんな疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
私も出版社で編集者として働いていた頃、同僚が副業でライターをしていたことが会社にバレて、大変な騒動になったことがありました。幸い、その同僚は処分を免れましたが、この経験から副業禁止の問題について深く考えるようになったのです。
現在、私はフリーランスのライターとして活動する傍ら、副業としてモデル業も行っています。この経験を通じて、副業禁止に関する法的な側面や、実際に副業を行う際のリスクと対策について詳しく調べてきました。
この記事では、「副業禁止は違法なのか?」という疑問に対して、法的根拠と実例をもとに分かりやすく解説します。
きっと、「副業 禁止 違法」とweb検索をしてこの記事に辿りついたあなたに、副業を検討している会社員の方が知っておくべき知識とリスク管理の方法をお伝えします。
副業の禁止は違法?企業はなぜ副業を禁止するのか

副業の背景
副業とは、従業員が本業以外の仕事に従事し、追加の収入を得る働き方を指します。近年、働き方改革や経済環境の変化を背景に、労働者の間で副業への関心が高まっています。従業員が副業を希望する理由は、収入の増加だけでなく、キャリアの幅を広げたり、新たなスキルを身につけたりするためなど多岐にわたります。
一方で、企業の中には従業員の副業を禁止する就業規則を設けている場合も少なくありません。しかし、2018年1月に厚生労働省が「モデル就業規則」を改訂し、副業を禁止する規定を削除したことにより、企業の副業解禁の動きが加速しました。これにより、従業員が就業規則を確認しながら副業にチャレンジしやすい環境が整いつつあります。今後も、企業の副業に対する姿勢や就業規則の見直しが進むことが予想されます。
そうなると、企業の担当者は法的にも副業の問題に対応せざるを得ません。この記事に辿り着いた企業側の担当者の皆様は、ぜひこちらの記事もご覧ください。
本業に支障が出るリスク
企業が副業を禁止する最大の理由は、従業員の本業に支障が出ることへの懸念です。副業により長時間労働となり、疲労が蓄積することで本業の生産性が低下する可能性があります。本業と副業の労働時間を通算して管理する必要があり、法定労働時間を超えないよう注意が必要です。
実際に私がモデル業と執筆業を両立していた頃、撮影が深夜まで続いた翌日は、どうしても集中力が散漫になってしまうことがありました。副業禁止を推進する企業側からすれば、従業員が副業によって本業のパフォーマンスを落とすリスクは避けたいと考えるのは自然なことです。
また、副業による疲労が原因で労災が発生した場合、企業は労働者の健康管理責任を問われる可能性もあります。このため、多くの企業は従業員の勤務時間外の活動についても一定の制限を設けているのです。
情報漏洩や競業避止義務
企業が副業を禁止する理由として、情報漏洩や競業避止義務の問題も大きな要因となっています。従業員が競合他社で副業を行ったり、業務上知り得た機密情報を副業先で活用したりする可能性を企業は懸念しています。
特にIT業界や金融業界など、機密性の高い情報を扱う企業では、従業員の副業に対してより厳しい姿勢を取る傾向があります。競業避止義務は、企業の競争力を保護するための重要な措置として位置づけられているのです。
私が出版社に勤務していた頃も、編集者が競合他社の雑誌でライターをすることは明確に禁止されていました。業界の人脈や企画情報が漏洩するリスクを考えると、企業側の懸念は理解できるものでした。
企業のイメージと統制
企業は自社のブランドイメージを守るため、従業員の副業を制限する場合があります。従業員が副業先で不祥事を起こした場合、本業の企業にもネガティブな影響が及ぶ可能性があるためです。
また、従業員の副業を認めることで、企業の統制が緩むことを懸念する経営陣も少なくありません。「会社への忠誠心が薄れるのではないか」「優秀な人材が流出してしまうのではないか」といった不安から、副業を禁止する企業も存在します。
ただし、こうした企業の考え方は時代とともに変化しており、優秀な人材の確保や従業員のスキルアップを目的として副業を解禁する企業も増えてきているのが現状です。
副業のメリットとデメリット
副業にはさまざまなメリットがあります。まず、労働者が副業を行うことで、収入を増やすことができるのは大きな魅力です。また、本業とは異なる分野で経験を積むことで、スキルアップやキャリア形成にもつながります。副業で得た知識や人脈が本業に活かされるケースも多く、自己成長の機会としても注目されています。
一方で、副業にはデメリットやリスクも存在します。副業に時間やエネルギーを割くことで、本業に支障が出る可能性がある点は、企業が副業を懸念する大きな理由の一つです。また、労働時間の管理が難しくなり、過重労働や健康リスクが高まることも考えられます。さらに、情報漏洩や企業の信用低下といったリスクも無視できません。
そのため、副業を始める際には、必ず自社の就業規則や労働契約書を確認し、企業の方針や副業に関するルールを理解することが重要です。副業はメリットだけでなく、リスクや法的側面も十分に考慮した上で、慎重に判断することが求められます。
副業禁止は違法になる可能性が!?

就業規則と労働基準法の関係
企業が副業を禁止する法的根拠は、主に就業規則にあります。労働基準法では、就業規則について「労働者が遵守すべき規律」を定めることができるとされており、副業禁止もその範囲に含まれると解釈されています。
しかし、就業規則で副業を禁止したからといって、すべてのケースで有効になるわけではありません。就業規則による副業禁止が認められるのは、「合理的な理由」がある場合に限られるというのが法的な判断基準となっています。
厚生労働省も、企業が副業を制限する場合には「労働者の自由な時間をどう利用するかは、基本的に労働者の自由である」との見解を示しており、無制限に副業を禁止することはできないとしています。
合理的理由がない全面禁止は無効の可能性
裁判例を見ると、副業禁止による懲戒処分が無効とされたケースが複数存在します。代表的な判例として「小川建設事件」では、労働者の勤務時間外の副業について、会社の業務に支障がない限り原則として自由であるとの判断が示されました。
また、「マンナ運輸事件」では、タクシー運転手がキャバレーでアルバイトをしていたことを理由とした懲戒解雇について、副業が本業に具体的な支障を与えていなかったことから、処分が無効とされています。
このように、合理的な理由がない副業禁止は無効となる可能性があり、企業側も慎重な判断が求められています。私の同僚のケースでも、最終的に副業が本業に支障を与えていなかったことが認められ、処分を免れることができたのです。
厚生労働省モデル就業規則改定と副業解禁の流れ
2018年、厚生労働省はモデル就業規則を改定し、副業・兼業について「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」との規定を設けました。この改定により、国として副業を推進する姿勢が明確に示されています。
厚生労働省は副業解禁のガイドラインも策定しており、企業が副業を制限できる場合として以下の4つを挙げています:
労務提供上の支障がある場合
企業秘密が漏洩する場合
会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
競業により、企業の利益を害する場合
これらの条件に該当しない限り、企業は従業員の副業を一律に禁止することはできないというのが、国の基本的な考え方となっています。
副業禁止の会社に勤める社員が気をつけること

副業を始める前に必ず確認すべきこと
副業を検討している従業員がまず行うべきなのは、自社の就業規則と雇用契約の内容確認です。
就業規則に副業に関する規定が必ず記載されているはずですので、以下の点をチェックしてください。
副業が全面的に禁止されているか
届出制や許可制となっているか
競業避止に関する具体的な規定
違反した場合の処分内容
私がフリーランスになる前に勤務していた出版社では、副業は届出制となっており、競合しない範囲であれば許可されていました。しかし、同じ業界でも会社によって規定は大きく異なります。
就業規則で副業が全面禁止されている場合でも、前述したように合理的理由がなければその規定自体が無効となる可能性があります。ただし、法的な争いを避けるためにも、まずは会社との対話を試みることをお勧めします。
副業がバレる仕組みとそのリスク
副業を行っている従業員が会社にバレる主な経路として、以下のようなものがあります。
住民税の金額変化
最も一般的な発覚パターンです。副業収入があると住民税が増額され、会社の給与担当者が気づく場合があります。
SNSや知人からの情報漏洩
モデル業を副業で行っている私も、この点は非常に注意しています。撮影現場の写真をSNSに投稿する際は、本業の同僚に見られる可能性を常に考慮しています。
業務への影響
副業による疲労で本業のパフォーマンスが低下すると、上司から副業の有無を問われる場合があります。
副業がバレた場合のリスクとしては、就業規則に基づく懲戒処分を受ける可能性や、最悪の場合は解雇処分を受ける可能性があります。ただし、前述したように合理的理由のない処分は無効となる可能性もあります。
バレないための工夫とリスク管理
副業を行う際のリスク管理として、以下の点に注意することが重要です。
税務面の対策
副業収入の住民税については、確定申告の際に「普通徴収」を選択することで、会社にバレるリスクを軽減できます。ただし、これは完全な対策ではないため、税理士に相談することをお勧めします。
情報管理の徹底
私がモデル業を行う際は、撮影現場では本名ではなく芸名を使用し、SNSでの投稿も慎重に行っています。また、撮影スケジュールが本業に影響しないよう、週末や休日に限定しています。
本業への影響の最小化
副業による疲労が本業に影響しないよう、体調管理と時間管理を徹底することが重要です。私の場合、撮影が長時間に及ぶ案件は断るなど、本業に支障が出ないよう調整しています。
また、副業を行う際は必ず家族の理解と協力を得ることも大切です。4歳の娘がいる私にとって、週末のモデル撮影は家族時間を削ることになるため、夫と事前に相談し、お互いが納得できる範囲で活動しています。
企業の責任と副業への対応

企業は、従業員の副業を認めるか、あるいは副業を禁止するかについて、社会的責任を持って対応する必要があります。従業員の副業を禁止する場合、企業が副業を禁止する理由としては、労働時間の適切な管理や、企業秘密の保護、人材の流出防止などが挙げられます。特に、従業員の副業が本業に悪影響を及ぼす可能性がある場合や、企業の利益を損なうリスクがある場合には、就業規則で副業を禁止することも合理的な対応といえるでしょう。
一方で、近年は副業を認める企業も増加傾向にあります。副業は労働者のキャリア形成やスキルアップを支援する手段として注目されており、企業が従業員の副業を認めることで、従業員のモチベーション向上や人材の定着につながるケースも見られます。企業が副業に対して柔軟な姿勢を持つことで、従業員の多様な働き方を支援し、企業全体の競争力強化にも寄与する可能性があります。
今後は、企業が従業員の副業に対してどのような方針を取るかが、企業の社会的責任や魅力にも直結していくでしょう。副業を禁止する場合も、認める場合も、従業員との十分な対話と明確なルール作りが不可欠です。
副業解禁の動きとこれからの働き方

副業解禁する企業が増える理由
近年、副業を解禁する企業が着実に増えています。従来の副業禁止から方針転換する企業の背景には、人材確保とイノベーション促進の目的があります。
優秀な人材の確保と定着
転職市場が活発化する中、副業を認めることで従業員の満足度を高め、優秀な人材の流出を防ぐ企業が増えています。特に若い世代の労働者は、副業による自己実現やスキルアップを重視する傾向があり、副業禁止の企業は敬遠されがちです。
イノベーションの創出
従業員が副業で得た知識や経験を本業に活かすことで、新しいアイデアやイノベーションが生まれる可能性があります。異業種での経験は、従来の発想にとらわれない斬新な視点をもたらすことが期待されています。
働き方の多様化への対応
コロナ禍を経て、働き方の多様化が急速に進みました。リモートワークの普及により、勤務時間外の時間をより有効活用したいと考える従業員が増加し、企業もこうしたニーズに応えることが求められています。
私自身も、モデル業で得た美容やファッションに関する知識が、ライター業での記事制作に活かされることが多々あります。このように、副業は本業にとってもプラスの効果をもたらす可能性があるのです。
これからのキャリアに副業を活かすには
副業を効果的にキャリアに活かすためには、戦略的なアプローチが重要です。
スキルアップと専門性の向上
副業は新しいスキルを習得する絶好の機会です。本業とは異なる分野でのチャレンジにより、市場価値の高い人材になることができます。私の場合、編集者としての文章力とモデルとしての表現力、両方のスキルを磨くことで、より幅広いライター案件を獲得できるようになりました。
収入源の多様化
単一の収入源に依存するリスクを分散することも、副業の大きなメリットです。特に不安定な経済情勢下では、複数の収入源を持つことが経済的な安定につながります。
将来の独立準備
副業は将来の独立や転職に向けた準備期間としても活用できます。私がフリーランスライターとして独立できたのも、会社員時代から副業として執筆活動を続けていたからこそです。
人脈の拡大
異なる業界での副業により、多様な人脈を築くことができます。この人脈が将来のビジネスチャンスにつながる可能性もあります。
笑顔で副業を続けるための心構え
副業を長期的に続けるためには、適切な心構えとバランス感覚が欠かせません。
ワークライフバランスの維持
副業に熱中するあまり、プライベートや家族との時間を犠牲にしてはいけません。私も初期の頃は仕事を詰め込みすぎて、娘との時間が取れずに反省したことがあります。現在は月の撮影回数を制限し、家族との時間を最優先にしています。
健康管理の重要性
本業と副業の両立には体力が必要です。十分な睡眠時間の確保と定期的な運動により、健康状態を維持することが重要です。私は趣味の運動を続けることで、忙しい日々でも体調を崩さずに済んでいます。
無理のない範囲での活動
副業は本業に支障が出ない範囲で行うことが前提です。収入を増やしたい気持ちは分かりますが、本業のパフォーマンス低下により職を失うリスクを考えると、慎重な判断が必要です。
長期的な視点での計画
副業を一時的な収入増加の手段ではなく、長期的なキャリア形成の一環として捉えることが大切です。目標を明確にし、そこに向かって着実にステップを踏んでいく姿勢を持ちましょう。
まとめ
副業禁止は直ちに違法というわけではありませんが、合理的な理由がない全面的な副業禁止は無効となる可能性があります。企業が副業を制限できるのは、本業に支障が出る場合、機密情報の漏洩リスクがある場合、競業により企業の利益を害する場合など、限定的な条件下に限られています。
副業を検討している方は、まず自社の就業規則を十分に確認し、リスクを理解した上で慎重に行動することが重要です。住民税の処理や情報管理など、バレないための工夫も必要ですが、何より本業に支障を与えないことが大前提となります。
私自身の経験からも、副業は正しい知識と適切なリスク管理があれば、キャリアアップや収入向上に大きく貢献する可能性があります。ただし、家族との時間や健康管理を犠牲にしてまで行うものではありません。
今後は副業解禁の流れがさらに加速すると予想されます。政府も副業を推進しており、多くの企業が方針転換を検討している状況です。この時代の変化を味方につけ、正しい知識と準備で自分らしい働き方を実現していただければと思います。
スキマ時間でできる副業にどんなものがあるか、気になる方はこちらの記事もご覧ください。
副業に関する疑問や不安があれば、労働問題に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。法的なリスクを適切に評価し、安全に副業を行うための道筋を見つけることが、成功への第一歩となるでしょう。