副業とは?会社にバレない範囲と始め方、現役ママライターが解説!
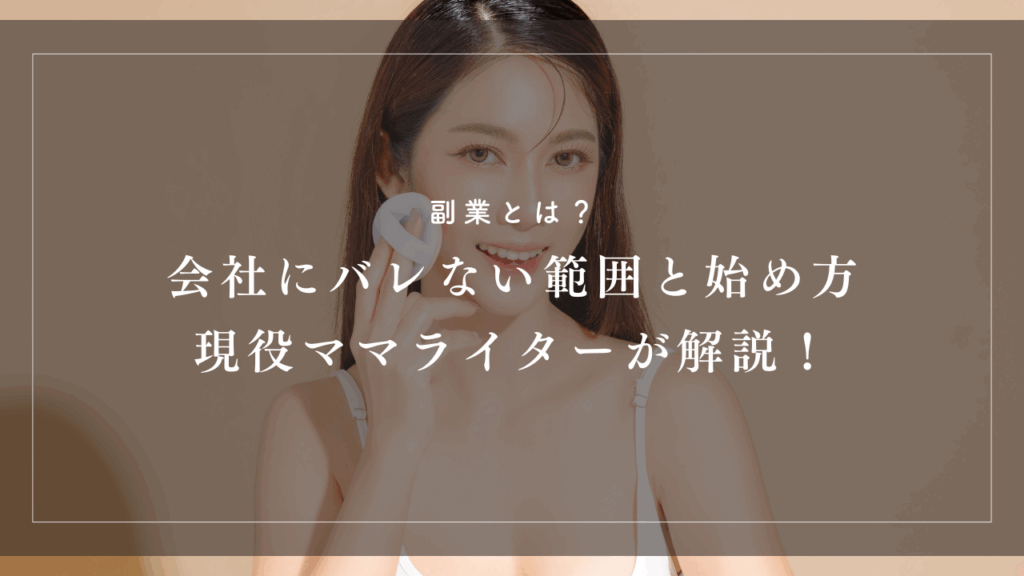
こんにちは、2児の母でありながら、ライターとして、そして副業モデルとしても活動している佐藤です。昨今、「副業元年」とも言われるほど、副業への関心が高まっていますね。実際、厚生労働省が2018年に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表して以来、副業を容認する企業も増えてきました。
私自身も、出産後のキャリアの変化と家計のやりくりを考えるなかで、本業のライターとしての仕事に加えて、副業モデルとして一歩を踏み出した経験があります。最初は不安もありましたが、今では子育てと両立しながら、充実した複数の仕事を楽しんでいます。
「副業とは何か」「どこまでが副業?」「会社にバレない範囲は?」「税金はどうなるの?」…こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。この記事では、私の経験も交えながら、副業に関する基本的な知識から始め方まで、分かりやすく解説していきます。
副業とは?──定義と兼業・複業との違い

まず基本的な「副業とは」という定義から説明しましょう。多くの方が混同しがちな「兼業」「複業」との違いについても触れていきます。
副業の基本定義と厚生労働省の見解
副業とは本業以外の仕事で収入を得る活動のことを指します。厚生労働省では「労働者が、勤務先と異なる企業や団体等で、また自ら起業するなどして、主たる雇用関係以外の仕事に従事すること」と定義しています。
一般的には会社員として働きながら、休日や平日の夜間などを利用して別の仕事をする形態が多く見られます。「ダブルワーク」という言葉も使われることがありますが、こちらは主に複数の会社で雇用されている状態を指すことが多いです。
厚生労働省では、副業・兼業の促進に関するガイドラインを策定し、モデル就業規則でも副業・兼業を前向きに捉える方向で改定が行われています。現在のモデル就業規則では「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」という一文が加えられました。
つまり、厚生労働省としては、原則的に副業を禁止するのではなく、容認する方向へと政策転換が図られているのです。特に、副業とは本業の時間外に行う仕事であり、就業規則で禁止されている場合でも許される可能性がある副業の種類やリスクについても考慮されています。
兼業・複業との違いを図解でわかりやすく
「副業」「兼業」「複業」という言葉、違いがわかりにくいですよね。実は明確な区分はなく、使われる文脈によって意味合いが少し異なります。
用語としての違い:
副業:主に本業があって、それ以外の仕事で収入を得る活動
兼業:複数の仕事を同時に行うこと(本業と副業の区別が曖昧な場合も)
複業:近年よく使われるようになった言葉で、複数の専門性を持ち、それぞれの仕事で価値を発揮する働き方
私の場合を例に挙げると、ライターとしての仕事が本業で、それに加えてモデルの仕事をしているため「副業モデル」と表現しています。でも最近では「複業」という考え方も広がり、「ライター×モデル」というように、異なる専門領域を持つ複合的な働き方としても捉えられます。
実際の働き方の例:
会社員+Webライター
教師+オンライン講師
エンジニア+フリーランスのプログラマー
会社員+副業モデル(私の場合)
副業のメリット
副業がバレる?会社員が知っておくべきルールと就業規則

副業を始める前に心配になるのが、「会社にバレないか」「就業規則に違反しないか」という点ではないでしょうか。特に、副業の時間や仕事量を適切に調整しないと、本業に支障が出る可能性が高いです。この章では、副業と就業規則の関係について解説します。
「副業禁止」の就業規則を確認しよう
まず最初に確認すべきは、勤務先の就業規則です。日本の多くの企業では、かつては副業禁止が一般的でしたが、現在は副業を容認する流れになっています。
とはいえ、依然として副業禁止の企業も存在します。就業規則を確認しても「副業禁止」と明記されている場合や、「会社の許可を得て行う」という条件付きの場合もあります。副業を始める際は、まず自社の就業規則を確認して、禁止されているかどうかをチェックしましょう。
特に日本の大手企業や公務員の場合は、副業が禁止されていることが多いので注意が必要です。ただし、厚生労働省のガイドラインでは「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」と明記されているため、企業側も徐々に副業容認へと方針を変えつつあります。
副業が会社にバレる主な原因
副業が会社にバレる主な原因としては、以下の点が挙げられます:
住民税の通知:副業での収入が20万円を超えると、住民税の金額が変わります。会社が従業員の住民税を給与から天引きする「特別徴収」を採用している場合、翌年5〜6月頃に自治体から会社に通知が行き、副業の存在が明らかになる可能性があります。
SNSでの発信:副業の内容や実績をSNSに投稿することで、同僚や上司の目に触れる可能性があります。特に私のような副業モデルの場合は、写真が公開されることもあるため注意が必要です。
クラウドソーシングの報酬振込:会社と同じ銀行口座を使っていると、通帳記帳時に副業の報酬が記録されます。家族や会社の経理担当者の目に触れる可能性も。
同業他社・取引先での副業:本業と関連性が高い分野で副業をしていると、業界内での噂になりやすく、会社に情報が流れる可能性があります。
会社にバレずに副業するためのコツ
就業規則で副業が禁止されている場合でも、合法的な範囲で副業を行いたいという方のために、いくつかのコツをご紹介します:
住民税の納付方法を変更:給与から天引きされる「特別徴収」ではなく、自分で納付する「普通徴収」に切り替えることで、会社に副業の存在が分かりにくくなります。住民税の申告時に「自分で納付」にチェックを入れるだけです。
副業専用の銀行口座を開設:副業の報酬を受け取るための専用口座を作ると、本業の給与明細と区別できます。
副業のジャンルを本業と分ける:本業と全く異なる分野の副業を選ぶことで、利益相反や情報漏洩のリスクを減らせます。
実際に私が副業モデルを始めた際は、撮影が平日の昼間にあることも多く、本業のライターとしての仕事との両立が課題でした。そこで、ライターの仕事は朝早くと夜に集中し、撮影は午後にセッティングしてもらうなど、スケジュール調整を工夫しました。また、モデルとしての活動は本業のライティングとは全く別の分野だったため、利益相反のリスクもありませんでした。
副業を始める前に知っておくべき注意点

副業を始めると新たな収入を得られる一方で、いくつか注意すべきポイントもあります。特に税金や時間管理、本業への影響については事前に理解しておく必要があります。
税金・確定申告に関する基礎知識
副業での収入には当然税金がかかります。ここでは、副業を始める際に知っておきたい税金の基礎知識をご紹介します。
年間20万円の壁:副業での収入が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば申告は不要ですが、収入の記録は必ず残しておきましょう。私の場合、副業モデルとしての収入は年によって変動があるため、初年度は収入が少なくても記録をつける習慣をつけました。
雑所得と事業所得の違い:副業での収入は、その性質によって「雑所得」または「事業所得」に分類されます。
雑所得:副業が継続的ではなく、臨時的・一時的な場合(例:たまにする記事執筆やアンケートモニター)
事業所得:副業が継続的で、事業性があると認められる場合(例:定期的な執筆活動やコンサルティング)
青色申告と白色申告:事業所得として申告する場合、青色申告か白色申告かを選べます。
青色申告:最大65万円の控除が受けられるが、複式簿記での記帳が必要
白色申告:手続きが簡単だが、控除額は10万円
私の場合、副業が本格化してきたタイミングで税理士さんに相談し、青色申告に切り替えました。最初は手間に感じましたが、確定申告ソフトを使うことで負担を減らせています。
また、副業の収入が多くなると、住民税や社会保険料への影響も出てきます。特に扶養内で働いている方は、年間収入が103万円や130万円を超えると税金や社会保険の状況が変わるので注意が必要です。
時間の使い方と本業への影響
副業を成功させる鍵は、副業と本業のバランスをうまく取ることです。私の場合、2人の子どもを育てながら本業と副業を両立させるために、かなり工夫してきました。
本業に支障を出さないスケジューリング:副業が原因で本業のパフォーマンスが落ちてしまうと、かえって収入減につながりかねません。副業と本業の時間や仕事量を適切に調整し、本業に支障が出ないように注意しています。私は以下のようなルールを設けています。
本業の締め切りがある日は副業を入れない
平日のライティング作業は朝5時〜7時と夜9時以降に集中させる
子どもが寝ている時間帯を有効活用する
リアルな一日の流れ:私の平日の典型的なスケジュールは以下の通りです。
5:00 起床、コーヒーを飲みながら本業のライティング作業
7:00 子どもたちの朝の準備、送り出し
9:00-14:00 本業のライティング作業または副業モデルの撮影
15:00 子どもたちのお迎え、夕食準備
19:00 子どもたちの就寝準備
21:00 子どもが寝た後、再び本業または副業の作業
23:00 就寝このようなタイムスケジュールを組むことで、子育てをしながらでも副業との両立が可能になっています。もちろん、体調管理や休息も大切なので、週末は家族との時間を優先するようにしています。
労働時間と労働基準法のチェックポイント
副業を行う際は、労働時間の制限にも注意が必要です。労働基準法では、本業と副業の労働時間を合計して考える「労働時間通算」の原則があります。
過重労働に注意:法律上、本業と副業を合わせた労働時間が週40時間、1日8時間を超えると、超過分は残業となります。過労による健康被害を防ぐためにも、適切な休息時間を確保しましょう。
労働時間の通算問題:現在の制度では、会社は従業員の副業先での労働時間を把握する義務がありますが、実際には難しいケースが多いです。自己管理が重要になってきます。
私の場合は、副業モデルの活動は月に2〜3回程度と頻度が限られているため、過重労働になるリスクは低いですが、それでも体調管理には気を配っています。本業も副業も「無理なく続けられる範囲」を見極めることが大切です。
おすすめの副業5選|私がやってよかった副業も紹介

ここからは、私自身の経験も踏まえて、おすすめの副業をご紹介します。どの副業も始めやすく、子育て中の方でも取り組みやすいものばかりです。
1. Webライター
特徴:初期投資が少なく、パソコンとインターネット環境があれば始められます。クラウドソーシングサイトから小さな案件を受注し、実績を積み重ねていくことができます。
向いている人:文章を書くのが得意な人、特定の分野に詳しい人、調べものが好きな人
私自身、本業として行っていますが、副業としても始めやすいおすすめの仕事です。特に子育ての知識や経験を活かして「育児」「教育」関連の記事を書くと、自分の経験が価値になります。
2. ハンドメイド販売
特徴:趣味の延長として始められ、自分のペースで作品を作れます。ミンネやCreemaなどのプラットフォームを利用すれば、販売ルートの確保も容易です。
向いている人:手先が器用な人、創作活動が好きな人、オリジナリティを表現したい人
私の友人は子どもの洋服を手作りする技術を活かし、ハンドメイドの子ども服を販売して月に5万円ほどの副収入を得ています。
3. 写真販売
特徴:スマートフォンのカメラでも高品質な写真が撮れる時代です。PIXTA、Shutterstockなどのストックフォトサービスに写真を登録して販売できます。
向いている人:写真が好きな人、視覚的なセンスがある人、日常の何気ない瞬間を切り取るのが得意な人
子育て中のママが撮る「リアルな子どもの表情」や「日常の家庭風景」は需要が高く、私も副業の一つとして取り組んでいます。
4. ポイ活・アンケート回答
特徴:スキマ時間を活用しやすく、特別なスキルがなくても始められます。ポイントサイトでのショッピングやアンケート回答でポイントを貯めて現金化します。
向いている人:隙間時間を有効活用したい人、コツコツと作業を積み重ねられる人
子どもが昼寝している間や、病院の待ち時間などを活用できるので、子育て中のママにもおすすめです。
5. 副業モデル
特徴:撮影モデルとしてアパレルやコスメ、エステなどの広告に出演します。単発の仕事が多く、撮影は平日の昼間に行われることが多いです。
向いている人:自分を表現するのが好きな人、人前に出ることに抵抗がない人、フレキシブルなスケジュールで働ける人
私自身が実際に行っている副業で、意外にもハードルは高くありません。「一般人モデル」や「リアルユーザーモデル」として起用されるケースも多く、年齢や体型を問わない案件も増えています。子育て中の「ママモデル」としての需要もあり、子連れOKの撮影もあります。
副業を始めるステップとツール紹介

副業を始めたいけれど、何から手をつければいいか分からない…そんな方のために、具体的なステップをご紹介します。
STEP1:副業目的の明確化
副業を始める前に、「なぜ副業をしたいのか」という目的を明確にしましょう。単に収入アップを目指すのか、新しいスキルを身につけたいのか、それとも将来の独立を視野に入れているのか。目的によって、選ぶべき副業の種類や取り組み方が変わってきます。
私の場合は、「子育てのために時間の融通が利く働き方をしたい」「ライターとしてのスキルを活かしつつ、新しい経験も積みたい」という目的から副業モデルを選びました。
STEP2:就業規則の確認とリスクの理解
前述したように、勤務先の就業規則を確認して副業が禁止されていないかチェックすることが大切です。就業規則に違反すると、最悪の場合は懲戒処分の対象になることもあります。
また、副業に取り組む際のリスク(健康面、本業への影響、税金・社会保険の変動など)も理解しておきましょう。
STEP3:小さく始めてみる
いきなり大きな案件に挑戦するのではなく、小さな仕事から始めることをおすすめします。例えば:
クラウドワークス:文章作成やデータ入力など、さまざまな仕事があります
ココナラ:自分のスキルを販売できるサービス
タイムチケット:時間単位でスキルを販売するプラットフォーム
私も副業モデルを始める前に、小さな案件から挑戦して、自分のペースを掴むことから始めました。無理なく続けられる範囲を見極めることが大切です。
STEP4:収入管理と申告方法を整える
副業での収入は必ず記録し、確定申告が必要な場合は適切に申告しましょう。収入管理には以下のようなツールが便利です:
freee:クラウド会計ソフト。領収書をスマホで撮影して自動入力できる
マネーフォワード:家計簿アプリとしても使えて、副業の収支管理も可能
Googleスプレッドシート:無料で使えて、自分好みにカスタマイズできる
私は最初はGoogleスプレッドシートで管理していましたが、収入が増えてきたタイミングでfreeeに移行しました。確定申告もスムーズにできるようになり、時間の節約になっています。
副業の促進に関するガイドライン
厚生労働省は、副業の促進に関するガイドラインを発表しています。このガイドラインでは、副業をする労働者の権利と義務について明確に定められています。特に、副業が本業に支障をきたさないようにすることが強調されています。例えば、副業の時間管理や労働時間の調整が求められます。
また、ガイドラインでは、労働者が健康を維持できるようにするための措置も述べられています。過労やストレスを避けるために、適切な休息時間を確保することが推奨されています。企業側も、副業をする労働者に対して必要な情報を提供し、安心して副業を行える環境を整えることが求められています。
さらに、企業が副業をする労働者に対して取るべき対応についても具体的に示されています。例えば、副業に関する相談窓口の設置や、労働者が副業を行う際のガイドラインの提供などが挙げられます。これにより、労働者が安心して副業に取り組むことができる環境が整えられています。
副業に関するよくある質問

最後に、副業に関してよく質問される内容をQ&A形式でまとめました。
Q1: 副業っていくらから申告が必要?
A: 基本的には年間の副業収入が20万円を超えた場合に確定申告が必要です。ただし、20万円以下でも記録は残しておきましょう。また、本業が給与所得で年末調整を受けている方は、副業の所得が20万円以下であれば申告不要です。
Q2: 副業がバレたらクビになる?
A: 就業規則で副業が明確に禁止されている場合、発覚すると懲戒処分の対象になる可能性があります。ただし、すぐにクビになるケースは稀で、まずは注意や警告が行われることが多いです。副業禁止の規定がある会社でも、会社に申請して許可を得られれば副業ができる場合もあります。
Q3: 扶養内で副業できる?
A: 配偶者の扶養に入っている場合、年間収入が103万円(所得税の壁)や130万円(社会保険の壁)以内であれば、扶養内で副業することが可能です。ただし、本業と副業の収入を合算した金額が基準となるので注意が必要です。
Q4: 子育て中の副業のおすすめは?
A: 子育て中は時間の制約があるため、隙間時間を活用できるWebライターやポイ活、在宅ワークがおすすめです。また、子育ての経験を活かした「ママモデル」や子ども向け商品のモニター、子育てコラムの執筆なども選択肢になります。私自身は子どもが保育園に行っている時間や寝た後の時間を活用して副業をしています。
副業の参考文献
副業に関する参考文献は多岐にわたります。以下に、副業に関する主要な参考文献をいくつかご紹介します。
厚生労働省「副業の促進に関するガイドライン」:副業を行う際の基本的なルールや注意点が詳しく解説されています。
総務省「副業に関する調査報告」:副業の現状やトレンド、労働者の意識調査結果がまとめられています。
日本経済新聞「副業が広がる背景と今後」:副業が広がる背景や今後の展望について、経済的な視点から分析されています。
日経ビジネス「副業で収入を増やす方法」:具体的な副業の始め方や収入を増やすための戦略が紹介されています。
Forbes「副業をするべき理由」:副業を行うメリットや成功事例が取り上げられています。
これらの文献を参考にすることで、副業に関する知識を深め、より効果的に副業を進めることができるでしょう。
まとめ
「副業とは?」と悩むすべての方へ、この記事がお役に立てば嬉しいです。副業は単に収入を増やすだけでなく、新しいスキルや人脈を広げるチャンスでもあります。
私自身、副業モデルを始めてから、新しい出会いや経験が増え、本業のライティングにも良い影響を与えています。もちろん、子育てとの両立は簡単ではなく、時には疲れ切ることもありますが、「自分のペースで無理なく続ける」ことを心がければ、充実した副業ライフを送ることができます。
副業を始める際は、就業規則の確認や税金の知識など、基本的なルールを押さえつつ、小さな一歩から踏み出してみましょう。リスクを最小限に抑えながら始められる方法はたくさんあります。あなたにぴったりの副業が見つかることを願っています!
Modelicでは、フリーモデルとクライアントをマッチングするサービスを提供しています。
副業でできるモデルの仕事に興味がある方は、ぜひモデル登録をお願いします。